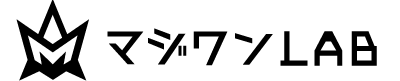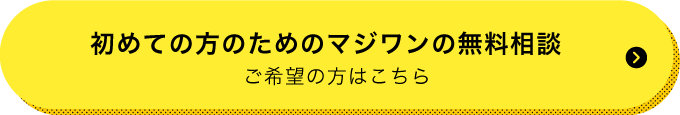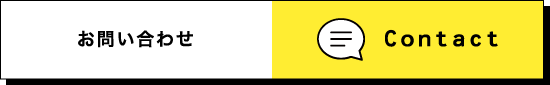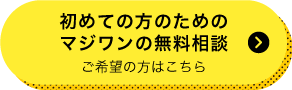クッションページの今後2025 ①

クッションページの「今」のかたち
これまでいくつかクッションページに関する記載をさせていただきました。
その中で最近の変化について解説をしたいと思います。
最近のクッションページづくりには、確かな“型”がありつつも、進化の波もしっかりきています。なかでも、いま意識したい3つのポイントをご紹介します。
- 記事スタイルの基本を押さえる
まず土台となるのは、これまで主流だった「PASONA」の構成です。
Problem(課題提示)→Affinity(共感)→Solution(解決策)→Offer(提案)→Narrowing down(限定)→Action(行動)という流れをきちんと理解して、基本を外さないことが大切です。 - ファーストビューに動画を使う
最近では、記事だけで勝負するのが難しくなってきました。審査も以前より厳しくなっていて、従来の構成だけでは通りづらい場面も。
そこで登場したのが「ファーストビュー動画」。
ページの冒頭に動画を配置し、視覚と聴覚に一気に訴えかけることで、強いインパクトと滞在率アップが期待できます。 - 最後にアンケートを設置する
読み終わった後に、アンケートを設けるのも効果的な工夫のひとつです。
参加型のステップを加えることで、ユーザーのアクション意欲を自然に引き出し、次ページ(LPなど)へのスムーズな導線をつくれます。
“読むだけ”で終わらせず、“関わる”流れに変えることがポイントです。
これらの3つの要素を踏まえた設計が、現時点での「今どきのクッションページ」のベースといえます。
言い換えるなら、ここが“第一段階”としての完成形。
ここから先、どんなアップデートが起きるのか──その変化を見据える準備も、もう始まっているのかもしれません。
ホワイト広告・大手企業に求められる「次のスタイル」
これまでお伝えしてきた「完成形」とされるクッションページのかたちがある一方で、いま、新たなテーマとして注目されているのが――大手企業や製薬会社など、レギュレーションが厳しい企業にどう対応するかという点です。
こうした企業では、いわゆる“煽り”や“強めの訴求”に敏感で、薬機法や社内基準を厳格に守る必要があるため、一歩引いた表現や、より誠実なトーンが求められます。
つまり、「売るための文章」ではなく、“信頼を届ける文章”へのシフトが求められている――
それが、“ホワイト系”企業におけるクッションページの新たな潮流です。
この変化にどう対応していくか。
これからの時代に向けて、制作側としてもしっかりと考えていく必要がありそうです。
ホワイト広告で注目される“今”のスタイルとは?
大手企業や製薬会社など、いわゆる“ホワイト系”の広告において注目されているのが、以下の2つのクッションページスタイルです。
● アンケート単体型
「これはただの市場調査です」という見せ方ができる、シンプルなアンケート形式。
過剰な訴求を避けつつも、興味がある人だけが自然と参加できる構成になっているため、薬機法や社内レギュレーションが厳しい企業から高く評価されています。
とくに「参加すること」にフォーカスしたこの形式は、煽らずにユーザーとつながる“入り口”として優秀なスタイルです。
● ニュース記事風スタイル
もうひとつ注目されているのが、ニュース記事風に構成されたページ。
ライターの語り口ではなく、第三者的な視点や客観性を持たせることで、より信頼性の高い印象を与えられます。
ニュース記事風スタイルには、さらに2つの方向性があるのがポイントです。
1)既存商品との差別化型
あからさまに他社製品を否定するのではなく、「これまでは◯◯が難しかった」→「でもこの商品なら…」という流れで、やんわりと差別化を図る方法。
景表法に抵触しないよう、慎重に言葉を選びながらストーリーを組み立てていきます。
2)記者発表・プレスリリース型
まるで企業のプレスリリースのように、“新しいニュース”として打ち出すスタイルです。とくに信頼性が重視される大手企業では、「○○社が開発した新技術」や「専門家が登壇した発表会」といった切り口が有効。
実際の新聞やメディア風の構成にすることで、話題性と信頼性の両立が図れます。
まとめ
ホワイト広告の現場で注目されているスタイルは、主に以下の3つに整理できることを今回は解説しました。
- アンケート参加を促すスタイル
- やんわりとした比較で差別化を図るニュース風スタイル
- 話題性を活かしたプレスリリース型スタイル
なかでも、最近注目が集まっているのが「プレスリリースの再活用」。
派手な演出ではなく、事実ベースで“期待感”を丁寧に伝える方法として、今後さらに広がっていきそうです。
次回は、クッションページが今後どうなっていくのかについて解説します。