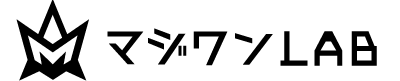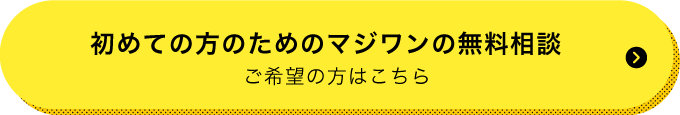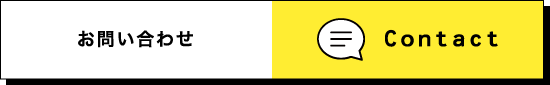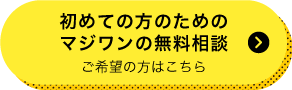なぜZ世代の購買行動は変化したのか?

Z世代は、今後の主要な購買層であると同時に、ブランドの評判やトレンドを形成するキーパーソンとして注目されています。そして現代の購買行動は、「モノを買う」から「意味を選ぶ」行為へと進化してきました。
では、なぜ人はその商品を選ぶのでしょうか?
本記事では、Z世代の購買行動の傾向とその背景を、前後編に分けて読み解いていきます。
前編では、団塊世代からZ世代までの価値観の変遷を、メディア環境や社会の変化とともに振り返りながら、購買行動の根底にある“評価軸”の移り変わりに迫ります。
Z世代の購買行動とは?
近年の調査では、Z世代には以下のような特徴が見られるとされています。
- SNSを信頼する
- 自己表現を重視する
- 画一化を嫌う
- コスパやタイパを重視する
「機能」よりも、「共感」や「文脈」に価値を見いだす傾向があり、従来の「モノ消費」から、共感や文脈で選ぶ「意味消費」へシフトしていると考えられています。
参照:デロイト トーマツ 2024年度「国内Z世代意識・購買行動調査」
さまざまなメディアでこうしたZ世代像が語られていますが、果たして“本当にそう”と言えるのでしょうか?
ここからは、各世代の消費行動の変化を振り返りながら、その前提や背景にある構造的な変化について整理していきたいと思います。
集団と同調の消費が主だった団塊世代
戦後のベビーブーム世代である団塊世代は、「みんなと同じ」が安心で、同じ商品を所有することがステータスだった時代に育ちました。高度経済成長期のテレビや新聞中心のマスメディアによる情報発信が、同調的消費を強く後押ししていたと考えられます。
当時の広告は一方通行にとどまっており、企業やブランドが提供する「正しさ」や「理想像」に従うかたちの消費が成立していました。企業が用意した価値観を受け入れることが“賢い選択”とみなされていた時代です。豊かさとはモノの所有を意味し、家電・自動車・マイホームなど、目に見える資産が消費の中心にありました。
ライフステージごとに進むべき「消費のレール」が存在し、商品は社会的地位や人生設計の象徴でもあったのです。
反発と個性化が始まった団塊ジュニア世代
団塊ジュニア世代は、親世代の価値観に一定の距離を取りつつも、社会の“空気”には敏感な傾向があります。「マス的価値観の残響」と「個の目覚め」が共存する過渡期の世代とも言えるでしょう。核家族化や教育の個別化が進んだことにより、「集団における正しさ」よりも「個人の意思」や「選択の自由」が重視されるようになりました。
この時代には、消費そのものが自己表現の手段へと転化していきます。90年代にはファッション・音楽・ライフスタイルといったジャンルでサブカルチャーが浸透し、ヒッピー文化や学生運動などのようなマイノリティ的価値観への憧れやマスメディアに流されない姿勢に「かっこよさ」を見いだす人が増えていきました。
一方で、バブル崩壊や就職氷河期を経て、消費行動に「慎重さ」や「懐疑」が入り込んだことも見逃せません。商品を選ぶ際には、単なる欲望ではなく、「それが本当に自分にとって意味があるのか?」という内省的な問いが強く意識されるようになったのです。
複合的な評価軸とメディアが交差するX世代・Y世代
X世代(おおよそ1965~1980年生まれ)は、マスメディアとパーソナルメディア(PC、携帯電話)が共存する時代に成人を迎えました。続くY世代(1981〜1996年生まれ)は、ソーシャルメディア黎明期のユーザーとして、消費者でありながら情報発信者としての感覚を育んだ世代です。
この頃から、企業やブランドに対する選定基準が、多面的かつ批判的なものへと変化しました。広告の表現だけでなく、企業が掲げるビジョンや社会課題へのスタンスなど、背景にある“文脈”が評価対象に加わるようになります。
また、選択の幅が広がった副作用として、膨大な選択肢に対する疲弊──いわゆる「選択のパラドックス」も顕在化します。一見、選択肢が多いほど自由に思えますが、選択肢が増えすぎることで判断に迷い、逆に満足度が下がるという心理現象です。何を選ぶべきか悩む場面が増え、結果として「信頼できる誰かの選択」に依存する傾向が強まりました。こうして、インフルエンサーやキュレーターのような“選択の代行者”が求められるようになります。
共感ベースで生きるデジタルネイティブのZ世代
Z世代(1997年以降生まれ)は、生まれたときからインターネットが存在し、SNSやYouTube、レビュー文化に囲まれて育ったデジタルネイティブです。購買行動の出発点は、もはや広告ではなく、TikTokやInstagramなどにおける日常的な「共感の瞬間」にあります。
情報収集が当たり前になっており、SNSコミュニティ内での承認欲求が購買を後押しします。情報の出どころは無数に存在し、あらゆる判断に「レビュー」や「レコメンド」が付きまとう社会の中で、自分の選択に対する根拠を持ちづらい現実があるのかもしれません。
そのため、Z世代は全体のトレンドを追うより、「自分の属するコミュニティ」で共有される価値を重視する傾向があります。購買行動は、まるで“共感するものへの投票”のようであり、自己の信念や文脈に沿ったブランドに支持を示すという態度が根づいています。
上記のような理由から、Z世代の中には多様な価値観が共存しており、単一モデルで語ることができません。マーケティングや広報においても、Z世代をひとくくりにするのではなく、複数の文脈とニーズを読み解く姿勢が不可欠となっているのです。
まとめ:“意味を選ぶ消費者”Z世代を生んだ4つの背景
改めて、Z世代が「意味」を選ぶ背景を整理すると、以下のような要因が交錯していると考えられます。
メディア構造の変容
発信者が企業から個人へ。SNSは友人・家族・趣味の仲間といった“近さ”を基準に価値を判断するツールとして浸透。社会的・経済的な不安定さ
将来に対する不安が強く、所有よりも機能・体験・共感を優先する消費が拡大。必要性や倫理性が強く問われる。倫理的消費の広がり
フェアトレード、ヴィーガン、サステナブル商品などを選ぶ背景には、個人の意志を社会的に表明する動機がある。アイデンティティの多様化
性別・国籍・文化的背景の混在が当たり前となり、自分の属する“コミュニティ”に適した選択が求められる。
Z世代にとって、消費とは“自分はこういう価値観を持っている”と示すためのシンボルのようなものであり、それを通じて他者とつながろうとする意志表明のひとつと言えるかもしれません。
以上です。
今回は、団塊世代からの消費に対する価値観の変化をたどりながら、Z世代の消費行動について紐解いてみました。後編では、Z世代が持つ“評価軸”をより具体的に分析し、企業がいま取るべきマーケティング戦略を考察します。
また別のコンテンツもご覧いただければと思います。